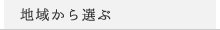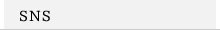����ʪ�ۿ��������£��ʪ���ػ���

�֤ʤ��ʤ������˻�ʤ��Ϸ��Ҥˤ����ʤ�٤��ꤱ��̤ν�Ф���סʡذ���ʪ���14�� ��
�������������˾Ǥ����̤ʤ�С����ä��������ޤ��Τ��ä������Ȥ��� �ν�Τ褦��û��̿���ä��Ȥ��Ƥ⡣��
�����ν���ϡ��ֻ��������סʤ����� �����ä� ����� ���餦�ỽ������˷��ٻϤ��� �ȤʤäƤ��ꡢ�ܻ����ȤǤϥ�����դ���ʬ���Ф뤳�κ�������ӻ��ʤ����ˡפȸƤФ���۲������Ф���Υ�������������ƻϤ�ޤ������ع������ʤμ½����������ä��Ƚ��餫�ʥ���ο����Ŧ�ߤˤ��ä��פ��ФΤ�������¿���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
�ܻ���5000ǯ�ۤ��������ǻϤޤä��ȸ����Ƥ��ꡢ���ܤǤϡ����������ס�3�����ˤˡֽ��ϻ������������¤��ۤ�פȤ������Ҥ����뤳�Ȥ��顢��������ˤϤ��Ǥ����ܤǤ����夬�������졢���Ѥ���Ƥ������Ȥ��狼��ޤ���8��������Ω�����ָŻ����פ�����ܽפˤϡ������������Τ����ȤȤ�˥����������ޤ줿�Ȥ��������꤬���ꡢ��������ܤ��ܻ�������������Ʊ�����餤�ν���������äƤ������Ȥ���¬����ޤ���
���Ȥ˵��Ťʼ�����⤿�餷�Ƥ���륫�����ϡ��֤������ޡפȸƤФ��Ⱦ�п����뤵�졢���̤��̴���Ǥϻ����Ȥ��ơ֤����餵�ޡפĤ������������Ǥ�����Ѥ���Ƥ��ޤ���
�֤����餵�ޡפΤ����Τ�1�ܡ�30cm�ˤ���������˽��ޤ����Ϥδ����������Ħ�ä��ꤷ����Τ�Ĥ����ۤΰ����Ťˤ��夻����ΤǤ����������������ܤ�����ä��Ȥ�������̼�������ס��Ϥ�̼�������ˤʤꡢ�Ȥ�˻��ǥ����������ޤ��Ȥ����áˤ˴�Ť��Ƥ��ޤ���
����μ��걡�Ȥ��������ˤϺ������������˸����«����ä��ϤΤ��Ф�Ω�Ľ��������������ꡢ̼���ϡ������ƥ�������Ż�����ä����ܤι����ϰ�Ǹ��Ѥ���Ƥ������Ȥ��狼��ޤ����ܻ����Ϥ����äϸŤ�������λŻ��ǡ����������ؤˤ����������椬���뤳�Ȥȴؤ�꤬����Τ��⤷��ޤ���
���ˤϡ�ŷ���ʥ���ɡˤ���ή���夤���ɱ�Ȥ�����������ɱ�ͤ���ʬ�λ�Ȱ������������ܤ��ܻ����������Ȥ����������ĤäƤ��ޤ��������äλĤ�ֻ��ƿ��ҡפϡ����ܤθ���ȯ�ͤ��Ϥȸ����Ƥ��ޤ������Ȥο����ϤȤ⤫�����ܻ����ڤ���������������줿���ڤʶȤǤ���Ȥ����͡��ΰռ������Ŀ����Ƥ����Ȥˤϰ㤤����ޤ���
���ܤ��ܻ��Ϲ��ͻ���˳��ͤο������Ⱥ��Ȥ��ƾ��夵�졢�����˲��Ū���ܻ����Ѥ���ȯ���줿���Ȥˤ�ꡢ���������δ����ޤ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ����������͢�Фϼ��פʳ��߳������ʤȤʤꡢ�ٹ�ʼ���ä��ۤ����ΤϤ�¸�ΤΤȤ���Ǥ���
���建�Ȥ�����餹�Ǥ˵פ���������Ǥ����ؤȤʤ�������ݤ���ڤǸ��μ��פϸ��äƤ��ޤ������ڤ����ʤ䤫�DzƤ��ä������ߤ��Ȥ������Ϥ�Ϥ�ۤ������ݤˤ��夨������̥�Ϥ�����ޤ����Ƕ�Ǥϵ��ڤ������Ǥ��륷�륯�˥å����ʤ�в�äƤ��ޤ��Τǡ����륯��Ż�äƤ���äԤ����ʵ�ʬ��̣��äƤߤ�Τ�褤�Ǥ��͡�
�����ε����ϡ�2013ǯ6��4�����ۿ����줿��NPOˡ����������ʸ�������������ޥ��������ʪ�ȡ��ΰ������Խ���ž�ܤ�����ΤǤ���
��餷��̤������Ϥ����롢����ͷ��٥��ޥ�����Τ���Ͽ
-

������ɮ�ۡ���ɮ����åץ֥饷���㺬���ɡ����
�Ȥ����֤����ˡ��Ф��ʤȤ��Ƥ��Ȥ�����������������ˤι�ɮ��
7,000��(�ǹ�7,700��)
-

��ɱϩ��ɱ�ٹ���Ĺ���ۡʥ饦��ɥե����ʡ��ˡ��ߥ���������
���ä���Ȥ��������Ρ�������ȴ���Υ饦��ɥե����ʡ�Ĺ���ۡ�
18,000��(�ǹ�19,800��)
SOLD OUT


 ɱ�ٹ�
ɱ�ٹ� ����
���� ���ںٹ�
���ںٹ� ���ڻ�ʪ
���ڻ�ʪ �ܼ���
�ܼ��� ð�����
ð����� �٤ù�
�٤ù� �ڤ��
�ڤ�� ����ɮ
����ɮ �»�
�»�