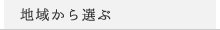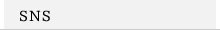ЎЪАёКӘЎЫҘҝҘЦЎјӨИӨөӨмӨҝөИҫНӨОӨ·ӨлӨ·Ў§ЎШҘБҘзҘҰЎЩ

ЎЦ»¶ӨкӨМӨмӨРёеӨПӨўӨҜӨҝӨЛӨКӨлІЦӨтЎЎ»ЧӨӨГОӨйӨәӨвӨЮӨЙӨҰДіӨ«ӨКЎЧ
ЎКБОАөКЧҫИЎШёЕәЈҪёЎЩЎЛ
ЎКМхЎ§»¶ӨГӨЖӨ·ӨЮӨЁӨРӨўӨИӨПӨҝӨАӨОҝРӨЛөўӨ№ІЦӨКӨОӨЛЎўӨҪӨҰӨИӨПГОӨйӨәІЦӨтГөӨ·ӨЖИфӨУПЗӨҰДіӨҝӨБӨЗӨўӨлӨіӨИӨиЎЈЎЛ
ӨіӨі°мҪөҙЦӨПіЖГПӨЗҝҝІЖЖьӨ¬ҙСВ¬ӨөӨмЎўГЩӨӨҪХӨ«Өй°мөӨӨЛҪйІЖӨОННБкӨИӨКӨкӨЮӨ·ӨҝӨ¬ЎўӨіӨОӨиӨҰӨКөӨёхӨЛӨКӨлӨИҘўҘІҘПӨОӨиӨҰӨКІЪӨдӨ«ӨКҘБҘзҘҰӨҝӨБӨОЙсӨ¬ё«ӨйӨмӨлӨиӨҰӨЛӨКӨкӨЮӨ№ЎЈНДГоӨ«ӨйӨөӨКӨ®ӨШЎўӨөӨКӨ®Ө«ӨйИюӨ·ӨӨА®ГоӨШӨИКСІҪӨ№ӨлҘБҘзҘҰӨПәЈӨвАОӨвҝАИлЕӘӨЗӨ№Ө¬ЎўёЕНиҘБҘзҘҰӨПҝНЎ№ӨЛӨЙӨОӨиӨҰӨЛВӘӨЁӨйӨмӨЖӨӯӨҝӨОӨЗӨ·ӨзӨҰӨ«ЎЈ
ҘБҘзҘҰӨИӨӨӨҰАёӨӯКӘӨПЎўёЕВеГж№сӨ«ӨйОоЕӘӨКВёәЯӨИ№НӨЁӨйӨмӨЖӨӨӨЮӨ·ӨҝЎЈҝБӨО»П№ДДлӨКӨЙө®ҝНӨОКиӨЛӨПЎўЎЦ¶в»ҪЎКӨӯӨуӨөӨуЎЛЎЧӨИёЖӨРӨмӨл»ҪӨОӨиӨҰӨКНДГоӨтҫЭӨГӨҝјцКӘӨ¬ВзОМӨЛЙыБтӨөӨмӨЖӨӨӨЮӨ·ӨҝЎЈЎЦұ©ІҪЕРАзЎКӨҰӨ«ӨИӨҰӨ»ӨуЎЛЎЧӨИӨПВОӨЛұ©Ө¬АёӨЁАзҝНӨИӨКӨГӨЖЕ·ӨШҫеӨлӨИӨӨӨҰГж№сӨОҝ®¶ДӨОӨіӨИӨЗӨ№Ө¬ЎўӨіӨмӨПӨЮӨөӨЛҝНАёӨтҪӘӨЁӨҝҝНӨ¬ҙҪӨОГжӨЗӨөӨКӨ®ӨИӨКӨкЎўҘБҘзҘҰӨЛҝКІҪӨ·ӨЖӨиӨкҫе°МӨОВёәЯӨЛКСІҪӨ№ӨлӨИӨӨӨҰҙкЛҫӨОЙҪӨмӨАӨИёАӨЁӨлӨЗӨ·ӨзӨҰЎЈІӯЖмӨЗӨПЎўҘБҘзҘҰӨПБДОоӨдҝАОоӨИ№НӨЁӨйӨмЎўӨҪӨО°Х»ЧӨтМдӨҰө§Еш»ХӨОӨЯӨ¬ДіМжӨОГеКӘӨтөцӨөӨмӨЮӨ·ӨҝЎЈҘБҘзҘҰӨПӨўӨОАӨӨИӨіӨОАӨӨтӨДӨКӨ°јцКӘӨЗӨўӨлӨИЖұ»юӨЛЎўКСІҪӨдәЖАёӨтҫЭД§Ө№ӨлөИҫНӨОӨ·ӨлӨ·ӨЗӨвӨўӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈ
Гж№сӨиӨкЕБӨпӨГӨҝӨИ№НӨЁӨйӨмӨлЖьЛЬӨЗӨОДіМжӨООт»ЛӨПёЕӨҜЎўАөБТұЎёжКӘӨЛӨвҘБҘзҘҰӨОКёННӨ¬ё«ӨйӨмӨЮӨ№ЎЈКҝ°В»юВеӨЛӨПЙрІИӨЗӨўӨкӨКӨ¬ӨйҪйӨбӨЖҫәЕВӨтөцӨөӨмЎўІнӨт№ҘӨуӨАКҝ»б°мМзӨОІИМжӨИӨ·ӨЖ°ҰНСӨөӨмӨЮӨ·ӨҝЎЈКҝІИМЗЛҙёеӨвӨҪӨОВеЙҪМжӨИӨөӨмЎўӨҪӨО°мВІӨтҫОӨ№ӨлІИӨПДіМжӨт»ИНСӨ·ӨЮӨ·ӨҝЎЈӨҪӨОјцҪСЕӘӨК°ХМЈ№зӨӨӨ«ӨйЎўіщБТ»юВеӨОЎЦМА·оөӯЎЧЎКЖЈё¶ДкІИЎЛӨдЎЦёгәК¶АЎЧӨЛӨПЎўҘБҘзҘҰ ӨО·ІЙсӨ¬ЙФөИӨКГыёхӨЗӨўӨлӨИӨӨӨҰөӯҪТӨ¬ё«ӨйӨмӨлӨіӨИӨвӨўӨкӨЮӨ·ӨҝӨ¬ЎўӨіӨОӨиӨҰӨКҝАИлАӯӨвЕЁӨт°ЪЙЭӨөӨ»ӨлӨҝӨбӨЛЙрІИӨ¬№ҘӨуӨЗДіМжӨт»ИНСӨ·ӨҝНэНіӨИӨвВӘӨЁӨйӨмӨКӨҜӨвӨўӨкӨЮӨ»ӨуЎЈ
»юВеӨ¬ІјӨкЎў№ҫёНӨОД®ҝНКёІҪӨ¬ОҙА№Ө№ӨләўӨЛӨКӨлӨИЎўҘБҘзҘҰӨОјцҪСЕӘӨК°ХМЈ№зӨӨӨПЗцӨмЎўКСІҪӨИәЖАёӨОҫЭД§ӨИӨ·ӨЖІОӨдіЁІиЎўКёННӨЛА№ӨуӨЛјиӨкЖюӨмӨйӨмӨлӨиӨҰӨЛӨКӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈёҪВеӨЗӨПЎўДіМжӨПЖұННӨЛөИҫНМжӨИӨ·ӨЖВӘӨЁӨйӨмӨДӨДӨвЎўҘБҘзҘҰӨ¬ІЦӨ«ӨйІЦӨШЙсӨӨ°ЬӨлӨөӨЮӨ«ӨйЎўә§ОйӨОҫмӨЛӨПӨХӨөӨпӨ·ӨҜӨКӨӨӨИ№НӨЁӨйӨмӨлӨіӨИӨвӨўӨкӨЮӨ№ЎЈәтәЈЎЦҘўҘІҘПЎЧӨИӨӨӨҰёАНХӨдӨҪӨОКБӨ¬ЎўұрӨдӨ«ӨЗІшӨ·ӨІӨКӨвӨОӨЛВӘӨЁӨйӨмӨлӨіӨИӨ¬ӨўӨлӨОӨПЎўӨвӨ·Ө«Ө№ӨлӨИӨҪӨОҝ§·БӨАӨұӨЗӨКӨҜЎўёЕВеӨ«ӨйӨОҝАИлЕӘӨКҘӨҘбЎјҘёӨ¬Ө«Ө№Ө«ӨЛЕБӨЁӨйӨмӨЖӨӨӨлӨ«ӨйӨКӨОӨ«ӨвГОӨмӨЮӨ»ӨуЎЈ
ўЁӨіӨОөӯ»цӨПЎў2012ЗҜ5·о2ЖьӨЛЗЫҝ®ӨөӨмӨҝЎўNPOЛЎҝНЖьЛЬЕБЕэКёІҪҝ¶¶ҪөЎ№ҪҘбЎјҘлҘЮҘ¬ҘёҘуЎШЙчКӘ»ИЎЩӨО°мЙфӨтКФҪёЎҰЕҫәЬӨ·ӨҝӨвӨОӨЗӨ№ЎЈ
КлӨйӨ·ӨтәМӨлҫрКуӨтӨӘЖПӨұӨ№ӨлЎўЎШПВН·ұсЎЩҘбЎјҘлҘЮҘ¬ҘёҘуӨОӨҙЕРПҝ
-

ЎЪЙұП©ЎҰЙұіЧәЩ№©ЎЫЎЎД№әвЙЫЎЎЎгДіЎҰҘФҘуҘҜЎд
ІЪӨдӨ«ӨККБӨЗҝҙӨвЙвӨӯО©ӨДЎў·ЪӨдӨ«ӨЗӨ·ӨГӨИӨкӨИјкӨЛӨКӨёӨаД№әвЙЫЎЈ
13,000ұЯ(АЗ№ю14,300ұЯ)
-

ЎЪЙұП©ЎҰЙұіЧәЩ№©ЎЫЎЎД№әвЙЫЎЎЎгДіЎҰҘЦҘлЎјЎд
ІЪӨдӨ«ӨККБӨЗҝҙӨвЙвӨӯО©ӨДЎў·ЪӨдӨ«ӨЗӨ·ӨГӨИӨкӨИјкӨЛӨКӨёӨаД№әвЙЫЎЈ
13,000ұЯ(АЗ№ю14,300ұЯ)
-

ЎЪЖаОЙЙ®ЎЫЎЎ№ИЙ®ЎҰҘкҘГҘЧҘЦҘйҘ·ЎЎЎгә¬НиЕЙЎҰјлЎд
№ИӨтә№Ө№»юҙЦӨтҫејБӨЛЎЈлРӨЁЙКӨИӨ·ӨЖӨӘ»ИӨӨӨӨӨҝӨАӨӯӨҝӨӨЎўөж¶ЛӨО№ИЙ®ЎЈ
7,000ұЯ(АЗ№ю7,700ұЯ)
-

ЎЪЙұП©ЎҰЙұіЧәЩ№©ЎЫД№әвЙЫЎКҘйҘҰҘуҘЙҘХҘЎҘ№ҘКЎјЎЛЎгҘлҘЯҘЁЎҰҘ°ҘкЎјҘуЎд
Ө·ӨГӨ«ӨкӨИӨ·ӨҝјБҙ¶ӨОЎўјэНЖОПИҙ·ІӨОҘйҘҰҘуҘЙҘХҘЎҘ№ҘКЎјД№әвЙЫЎЈ
18,000ұЯ(АЗ№ю19,800ұЯ)
SOLD OUT


 ЙұіЧәЩ№©
ЙұіЧәЩ№© °хЕБ
°хЕБ ҙуМЪәЩ№©
ҙуМЪәЩ№© ЕвМЪ»ШКӘ
ЕвМЪ»ШКӘ ЛЬјҝҙп
ЛЬјҝҙп Г°ёеҪММЛ
Г°ёеҪММЛ ӨЩӨГ№Г
ӨЩӨГ№Г АЪӨк»Т
АЪӨк»Т ЖаОЙЙ®
ЖаОЙЙ® ПВ»ж
ПВ»ж