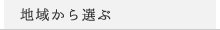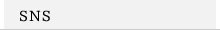【気象】秋本番を告げる:『霜』

「夜を寒み置く初霜をはらひつつ 草の枕にあまた旅寝ぬ」
(凡河内躬恒『古今和歌集』巻9)
(訳:夜が寒いので草花に降りた初霜を払いながら、旅の空の下、何度も寝ることであるよ。)
霜降の初侯は「霜始降(しも はじめて ふる)」で、この時期になると朝晩の空気がぴんと張り詰めるようになり、野山や庭先の草花にも霜が降り始めます。
日本語には「雨」や「雪」に関する多くの表現がありますが、「霜」にもさまざまな表現があります。冒頭の歌のように、10月下旬の「初霜」に始まり、八十八夜(立春から数えて88日目、5月2日頃)のころ、晩春に降りる最後の霜は「忘れ霜」「別れ霜」といいます。「朝霜」は消えやすいことから「消(け)」の枕詞としてはかなさを表現します。「霜朽ち」とはあかぎれ、しもやけ、ひび割れのことで、「霜枯る」とは霜にあたって草木が枯れること、「霜冴ゆる」とは霜がいっそう寒さを冴え渡らせるさまを表します。「霜を交える」とは頭髪に白髪が混じることで、霜が表現する物悲しさに、去り行く若い日々への惜別が込められた美しい表現です。
源氏物語の第30帖『藤袴』は、ちょうど今ごろの時期が舞台となっており、初霜がほの白く降りる深まる秋の風景の中に、美しい玉蔓と求婚者の兵部卿の宮との間で、「霜」を題材にした男女の妙味あるやりとりが交わされます。
「朝日さす光を見ても玉笹の 葉分けの霜を消たずもあらなむ」
(訳:朝日さす帝の御寵愛を受けられたとしても、葉に降りた霜のようにはかないわたしのことを忘れないでください)
兵部卿の宮が手紙につけたのは、霜がついたままの枯れた笹の葉でした。
玉蔓は、自身を葵の葉に見立てて宮の気持ちを感じていることを伝えます。
「心もて光に向かふ葵だに 朝おく霜をおのれやは消つ」
(訳:自分から光に向かう葵でさえ、朝置いた霜をどうして自分から消しましょうか)
都では優美な恋のツールとして使われた霜も、農村では作物に害を与えるものとして恐れられていました。水が自由に確保できなかった昔の田植えは梅雨時に行われたため、収穫は今よりも遅く、早霜は心配の種でした。
熊本県阿蘇氏の役犬原(やくいんばる)には、霜宮というお宮があり、ここでは毎年「火焚き神事」という霜除けのお祭りがあり、8月中旬から10月中旬までの56日間、火を焚き続けます。
昔、建磐龍命(タテイワタツノミコト)という神様が山に腰をかけて弓の稽古をしていましたが、矢を拾っていた鬼八という家来が100本目に飽きてしまい、矢を命に蹴り返しました。怒った命が鬼八を斬りつけると、鬼八は命を恨んで「天に昇ったら霜を降らせて五穀に害を与えよう。」と言って死んでいきます。以降毎年、その地は早霜に悩まされるようになり、困った命は鬼八に神として祀ることを約束して許しを請います。鬼八が「斬られた首が痛むから暖めてほしい」と言うので、命は霜宮を建てて火焚き神事を始めたということです。
そろそろ冬支度を始めるころに出会う霜、あなたは今年の初霜にどこで出会えるでしょうか。家の窓や植え込みの草木、踏みしめた土。早朝の蒼い空気の中に、寒さや冷たさ以上の何かを感じられるとよいですね。
※この記事は、2013年10月28日に配信された、NPO法人日本伝統文化振興機構メールマガジン『風物使』の一部を編集・転載したものです。
暮らしを彩る情報をお届けする、『和遊苑』メールマガジンのご登録


 姫革細工
姫革細工 印伝
印伝 寄木細工
寄木細工 唐木指物
唐木指物 丹後縮緬
丹後縮緬 べっ甲
べっ甲 切り子
切り子 奈良筆
奈良筆 土佐和紙
土佐和紙